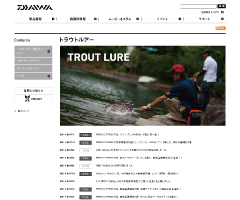水温20℃に近づくとアーリーサマーに突入
冷水系の魚で適水温が12~15℃であるトラウトは、高水温が苦手です。昨今の温暖化により、5月の連休を過ぎたころには高水温に対する攻略パターンを構築していく必要があります。高水温時の攻略術を、三浦さんに解説していただきます。
「水温が20℃に近づくとアーリーサマー。それを超えてくると、トラウトたちのコンディションはかなりバテ気味になってくるサマーシーズンに入っていきます。そんなトラウトたちに対して、通常の攻め方では、なかなか結果はついてきてくれません。高水温時の攻略パターンを覚え、それを実践していくことがとても大切になります」
水温の上昇でバテているトラウトたちは、ルアーに全く反応しない、というわけではありません。ルアーに興味を持つのですが、それを懸命に追ってくる元気がない状態です。このようなコンディションになっているトラウトに対して、マストになるルアーがマイクロスプーン。
「ほかのルアーが全く釣れないわけではないんですけど、高水温のときに一番実績を上げているのが1g以下のマイクロスプーンです。表層をデッドスローで引くことができて、追いの悪くなっているトラウトでもバイトしやすいタイミングを与えてあげることができます。今回のブログでは、高水温のアーリーサマー&サマーシーズンでのマイクロスプーンの使い方にスポットを当てて詳しくご紹介していきます」
「高水温で少々タフにはなりますが、そんな状態でもマイクロスプーンを的確に使いこなせれば、きちんと結果はついてきます」と三浦さん。
活性が上がっている朝と夕方の時間帯はチャンスタイム
高水温になるシーズンでは、特に集中して釣りをしてほしい時間帯が、朝のスタート時とエリアの営業終了前の夕方。朝の時間帯は、夜の間に下がった水温が上がりきっておらず、トラウトの活性も極端に下がっていないので比較的釣りやすいコンディションです。また、夕方の場合は、朝ほど水温は下がった状態ではないものの、強い日差しは落ち着き、水面の上を飛び交う虫も増えてきて、トラウトの活性は日中よりも上がった状態になっています。一日のトータルの釣果を上げるためには、朝と夕方の時間帯は集中して釣りましょう。
「おいしい時間帯を効率よく釣ることは、高水温時の攻略術のひとつといってもいいかもしれませんね」
表層狙いでは、センチ刻みのシビアなレンジ攻略が重要
高水温時は、表層が主戦場になります。
「表層がいい理由は、いくつか考えられます。風が吹いて波立つことで溶存酸素量が豊富になること。水面上を虫が飛び交いそれを意識するなど、いろいろなことが考えられます。ここをスローに攻めていけるマイクロスプーンが、高水温時のマストのルアーになるわけです」
表層のマイクロスプーンでは、水面直下から30㎝までの間を、いかに細かく刻んで攻めていけるかがキーになります。ほんのわずかなレンジの違いで、トラウトのマイクロスプーンに対する反応がガラリと変わってくるのです。
「最低でも5㎝刻み。できれば、1㎝刻みでもいいくらいです。例えば、スプーンの一部を水面上に出して大きな引き波を立ててくるバジング。さらにそれよりも数㎝だけレンジを下げて、水面がわずかに盛り上がり小さな引き波を引いてくる水面直下のリトリーブ。このわずかな違いだけで、反応が全く変わってくるんです。水面から水深30㎝までの間の表層レンジをいかに細かく刻んで引いてこられるかが、重要になります」
レンジを細かく刻むには、丁寧で正確なカウントダウンだけでなく、サイトで視認しながら引いてくることも大事になります。サイトではマイクロスプーンが泳いでいるレンジを確認できるだけでなく、その周辺のトラウトの反応も視認することができます。トラウトがあまり興味を示していないようならば、すぐにカラーをチェンジ。少しは反応するのだがバイトまでには至らないときには、レンジを変えてみるとよいでしょう。
水面上にボディを出して、大きな引き波を立てて引いてくるバジング。これで反応がなければ、あと数㎝レンジを下げて引いてみる。
夏バテで動きが鈍くなっているトラウトに対して、速いリトリーブは禁物。スローで巻いてくるのが基本中の基本
カラーローテーションのスタートは中間色から
カラーローテーションは他のシーズンと同様に、強い色から徐々に落としていくのが基本になります。しかし、スタートのときのカラーは異なります。
「ハイシーズンならばスタートはオレキンなどのゴールドベースの強い色から入ります。しかし、高水温時では強い色からではなく、中間色から入ります。カラシやライトピンクが中間色になります。暑さでバテているトラウトはナーバスになっていることが多く、いきなり強いカラーを見せることでプレッシャーをかけてしまう原因にもなりかねません。そのため、中間色から入るのが無難なんです。それに、中間色って視認しやすい色なのでサイトもしやすくなるんです」
中間色の次にはオリーブなどの地味な色へ少しずつ落としていくようにしますが、エリアによってはセカンドでシルバー系を入れるのも効果的な場合があります。グリメタやブルメタといったシルバーのリフレクションカラーに実績を持つエリアは意外と多く、そんなところでは、セカンドにシルバーカラーを挟んでみるのも効果的です。
表層がだめなら低層をチェックしてみる
高水温になるアーリーサマーやサマーシーズンは、表層がプロダクティブゾーンになりますが、常に表層ばかりで釣れるわけではありません。
「表層で反応が著しく鈍いときには、低層を攻めてみます。ボトムバンプやボトムスプーンで攻めるのもいいのですが、ここでもマイクロスプーンを使ってみてください。一度、着底させてから、巻き上げの軌道で引いてくるんです。ある程度巻きあげて、ボトムから離れたら、リーリングを止めて再度沈めせて着底。そして、また、巻き上げて巻いてくる。これを繰り返していきます。ウェイトが軽いので着水から着底まで時間がかかり、少々手返しは悪くなりますが、高水温で活性の下がったトラウトにはかなり有効な攻め方です。ちなみに、中層ですが、高水温のときは、あまりぱっとしません。表層がだめなら、思い切って低層狙いにスイッチ。そんな極端ともいえるレンジセレクトをしてみましょう」
マイクロスプーンと相性のいいのがエステルラインです。比重があり、低層をチェックしていくときでも、比較的速く着底させることができます。また、この素材は、軽いルアーでも飛距離を出しやすいのも特長です。PRESSO TYPE-Eは、エステル素材の長所はそのままに、比較的柔らかい設計になっています。ビギナーアングラーでも扱いやすく、おすすめです。
着水してから着底するまで、じっと我慢。着底したらボトムから巻き上げの軌道で引いてくる。手返しは悪くなるが、これもマイクロスプーンの効果的な使い方